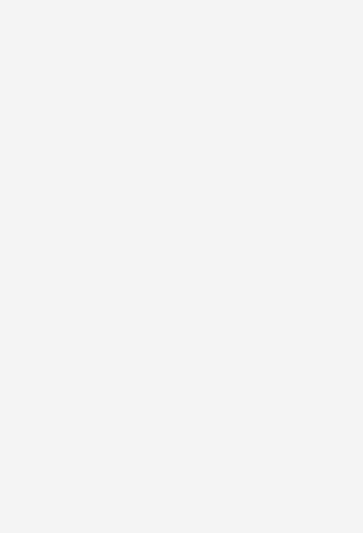書店員向け情報 HELP
出版者情報
書店注文情報
在庫ステータス
取引情報
東亜芸術 復刻版
- 出版社在庫情報
- 不明
- 初版年月日
- 2024年9月15日
- 書店発売日
- 2024年10月8日
- 登録日
- 2024年7月27日
- 最終更新日
- 2024年9月20日
紹介
明治の欧化政策からの転換期、大正初期に刻まれた東洋芸術の模索と抵抗―
「特に今日東亞の藝術が西歐藝術の威風の下に氣息奄々たるの實況を見るに及んで豈に長嘆大息せざるを得んや。吾徒茲に慨する所あり、同志胥謀り東亞藝術の恢興を以て目的と爲し、本誌發刊の舉を敢てするに至れり。江湖博雅の君子、若し吾徒と感を同ふせば冀くは、吾徒の斯舉を河漢視する勿れ。」(『東亜芸術』創刊号冒頭より抜粋)
明治期の西欧偏重の美術界の在り方が問い直され、首都では東京大正博覧会が盛況をあげるなか、近代以降の東洋の伝統に立脚した様々な芸術がなおざりにされていく現状に異を唱えた雑誌がうまれる。
「現代唯一之東洋文藝美術雑誌」と銘打たれ、書・画・建築・文藝・宗教・歴史と各界一級の人士を招き東亜の芸術の隆盛を目指した短命なる本誌は、転換期の唯一無二の営みを伝える。
目次
「時代を映し、時流に抗う異色の雑誌」
・一、書画に造詣の深い執筆陣、美術論から文明論まで展開
・二、東京大正博覧会書部門の審査不公に対する筆誅
・三、近代日中美術交流の視点から―廉泉と小萬柳堂書画コレクションをめぐる情報
・まとめ
前書きなど
『東亜藝術』が創刊したのは一九一四年の四月であった。年号では大正三年となるが、実際大正に改元した一九一二年の七月三十日から数えれば、この時点で日本は大正時代に入って僅か一年半しか経っていなかった。平塚らいてうが創刊した雑誌『青鞜』の発禁騒ぎが未だ落ち着かず、辰野金吾の設計による東京駅は竣工まであと八か月待たなければならなかった。第一次世界大戦が勃発する数か月前となる日本社会は、明治時代の雰囲気がまだ濃厚に残りつつ、新しい時代への期待が膨らみ、和やかで安定していた。
この頃の美術界の動向を振り返れば、これより三年前に、高村光太郎が「緑色の太陽」(一九一〇)を『スバル』に発表して芸術家の主観的表現の自由を唱え、武者小路実篤らが雑誌『白樺』(一九一〇)を創刊し、印象派以降の西洋美術を紹介し始めた。明治四十(一九〇七)年に創立した文部省美術展覧会(以下「文展」)は洋画、日本画各派の競り合い、拮抗が続き、第六回文展(一九一二)の日本画部門では新旧二科制が導入された。これに乗じて文展洋画部の二科併設運動も進行するところだった。国立美術館の建設や美術行政を管理する美術局を設置する必要性が唱えられ、美術界の動きが繁劇になるなかで、大正二年(一九一三)年十月に『美術新報』の運営者、東京美術学校教授の岩村透が『美術週報』を新たに創刊した。
明治期から大正期にかけての日本では、全面的な欧化政策を経て、それへの反省を含めた新しい文化の創出を模索するのが時代の主流であった。そんななかで、展覧会や美術教育、美術行政など現代にも通用する新しい美術制度の枠組みが急速に作られたのは目を見張る成果と言える。しかし一方で、従来日本文化の重要な一部であった書や文人画(南画)、篆刻など、東洋的思想や伝統中国文化への理解に基づく藝術がその新しい枠組みの外におかれ、ますます劣勢に立たされたのも争わない事実である。
このような状況に歯止めをかけようとして創刊した『東亜藝術』は、時代の動きをリアルタイムに反映しながらも、書画篆刻の伝統を振り返り、その将来を真剣に考える月刊誌として登場した。
版元から一言
今回の復刻資料は、一風珍しい大正初期の文化資料になります。
国会図書館に所蔵はなく、これまでの研究でも光があたってきたとは言えない雑誌と言えると思えます。
(大宅壮一文庫の雑誌創刊号紹介で、わずかに紹介されたことが唯一の事例かもしれないです。)
しかし、各界の一級の人物の名前が並び、第一次世界大戦前後という時代背景の面白さもあり、初めて見かけたときからぜひ研究者の皆様に紐解いていただきたいと感じておりました。
書道史関係の方々に問い合わせてもやはり知られていない模様、ただ、目次や内容から、多くの方に関心をお持ちいただけました。
そして、ちょうど京都に赴任された戦暁梅先生は丁度、『東亜藝術』でも交流が記される、廉泉(れんせん)という中国人の書画コレクターの研究取り組んでおられました。
お忙しい中解説に取り組んでいただき、「時代を映し、時流に抗う異色の雑誌」としてその価値をご紹介いただきました。
詳しくは解説をご覧いただければと思いますが、明治が終わってまもなく、芸術においても西洋追従が顕著である現状を振り返り、再考しようとした本誌は文化史のなかで重要なのだと感じます。
その創刊号には『白樺』五周年記念号の広告が巻頭に。
新しい芸術や感性が大きく育つ中で、「東亜」の芸術を見つめ、忌憚なき議論を展開しようとしていた営みが芸術・学術の分野横断を試みていたことはとても興味深いです。
他に、やはり面白いのは巻末の「個人消息」ですね。
どのように近況を仕入れているのかわからないですが、漱石や鴎外はじめ、横山大観や内藤湖南など、毎号数十名の著名人の様子短く報告しています。
大正期の文化が花開くその頃の、もう一つの試みをぜひお手元でご覧ください。
上記内容は本書刊行時のものです。