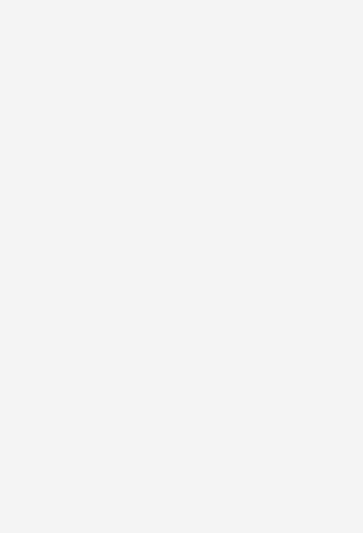書店員向け情報 HELP
出版者情報
書店注文情報
在庫ステータス
取引情報
家族と厄災
- 出版社在庫情報
- 在庫あり
- 初版年月日
- 2023年10月31日
- 書店発売日
- 2023年9月20日
- 登録日
- 2023年7月11日
- 最終更新日
- 2023年9月27日
重版情報
| 3刷 | 出来予定日: 2023-10-06 |
| MORE | |
| LESS | |
| 発売前重版決定 | |
紹介
非常事態の水面下で起きていたこととは。
新たな危機がやってきたとき、起こりうることとはーー。
パンデミックは、見えなかった、見ないようにしていた家族の問題を明るみにした。
家族で最も弱い立場に置かれた女性たちは、どのように生きのびようとしたのか。
家族問題に長年たずさわる臨床心理士が、その手さぐりと再生の軌跡を見つめた。社会の変化を視野に入れ、危機の時代の家族のありようを鮮烈に描写したエッセイ。
目次
まえがき
第1章 KSという暗号
カウンセラーを査定する
不穏な母
いつも誰かを背負って生きる
「かわいいよ」
フラッシュバックと痛み
私の手痛い失敗
侵入する記憶
第2章 飛んで行ってしまった心
何もなかったかのように
文字で埋めつくされたノート
不思議な感覚
私は存在している
KSがなくなる
言葉にこだわりけるつづけること
第3章 うしろ向きであることの意味
「未来志向」という強迫
whyからhowへ
ナラティヴセラピー
トラウマへの新しいアプローチ
「渦中」の危機と「その後」の危機
第4章 マスクを拒否する母
不穏な視線
心理的に距離をとる
母の遁走
華麗な日々が暗転
あふれる感情
第5章 親を許せという大合唱
四半世紀後のデジャヴ
「常識は変わらない」
加害と呼ぶことを許す言葉
あやまろうとしない親
戦うべき相手はだれか
第6章 母への罪悪感はなぜ生まれるのか
クライエントの三分の二は家族問題を抱えて来所する
名づけることの意味
罪悪感が生まれる背景
「あなたのために」という偽装された自己犠牲
第7章 「君を尊重するよ(正しいのはいつも俺だけど)」
孤立無援の日々
在宅勤務の夫
妻の納税額に衝撃
「君が望むなら」の本当の意味
責任転嫁と定義権の収奪
予期せぬ力関係の変化
第8章 私の体と母の体
予知夢
コロナ禍の葬儀
三世代の流れ
「私以外の誰がいるんですか?」
主客の逆転――かけがえのない存在になる
ケアをしながら、得られなかったケアを受ける
第9章 語りつづけることの意味
玄関の向こうは人権のない世界
世代間連鎖への恐怖
抵抗できない強い磁力
見知らぬ人に手を差し伸べるように
「仲間」の存在
語りつづけること
見知らぬ人になって母も変わった
代弁するということ
第10章 むき出しのまま社会と対峙する時代
時代の空気がわからなかったあのころ
重層的厄災
誰かに起きた暴力が、自分の痛みをよびさます
社会・国家とむき出しで対峙する時代
第11章 慣性の法則と変化の相克 ――一蓮托生を強いられる家族
非日常の日常化
カウンセリングが成立しなくなる?
変わりたくない社会が生むひずみ
例外として特権化される家族
DV相談件数と女性の自殺者数の増加
弱者化された主婦と女子高生
そしてウィズコロナの時代に
第12章 現実という名の太巻きをパクっとひと口で食べる
向田ドラマの男たち
「届かなさ」が人気の秘密
シンポシカン
盤石な地層のような現実
先端とは何か
コロナ禍の家族
あとがき――忘れないために、そして未来のために
主要参考資料一覧
前書きなど
まえがき
本書は二〇二〇年のパンデミックの緊急事態宣言下の混乱を背景にして生まれた。何か着地点が見えていたわけではない。でもあの不安と混迷の中で何か書かなければならない、そう思っていた。
大地が揺れるわけでもなく、荒れ狂う海に呑まれたわけでもない。ただ正体不明の未知のウイルスによる感染が拡大し、世界を、そして日本を巻き込んでいった。今から思えば、あれは幕開けに過ぎなかったのだが、新型コロナウイルスによるパンデミックが家族にどんな影響を与えるのだろうという視点だけはずっと変わらなかった。
本書のベースとなるウェブ連載を始めてからも、状況は予測を超える変化を見せ、あれほど毎日の報道をくいいるように眺めたことはなかったと思う。
感染は明らかに人とのつながりを媒介とするために、会話や食事など、飛沫が届く距離での接触こそ避けなければならないとされた。密室を避ける、人と出会い集うことを避けるという、「三密回避」「ディスタンス」が叫ばれたのである。
世界の歴史を見ると、疫病の蔓延は周期的に訪れている。東大寺の大仏の建立の理由のひとつに疫病流行があったことはよく知られているし、ルキノ・ヴィスコンティ監督の映画『ベニスに死す』(一九七一年)はコレラに感染した主人公が亡くなることがタイトルに反映されている。
新型コロナ感染症は、その三年後、二〇二三年の五月八日にインフルエンザ同様の5類に移行した。二〇二〇年の緊急事態宣言下、本書の企画がスタートしたのだから、三年後の実質上の転換期のころに単行本化の作業をしていることになる。
私は社会政策の専門家ではないが、この国はあらゆる政策の下支えを家族に求めてきたことをカウンセリングをとおして実感している。その家族をさらに下支えしてきたのが女性たち(祖母・母・妻・娘)であることは言うまでもない。二〇一一年に起きた東日本大震災を思い出す。三月一一日の直後からあらゆるメディアをとおして「絆」が叫ばれたこと、それも横軸の夫婦ではなく、縦軸の親子の絆が中心だったことを忘れることはできない。
日本の福祉の不備を「家族の絆」や「家族愛」といった言葉がカバーしていることは、精神科医療や子どもの発達障害をめぐる状況を見ても明らかだ。子どもに何か問題が起きれば、父と母のどちらが仕事を犠牲にするか。家族の支えが必要と語る援助者は、家族=母を前提としていたりする。後は家族がなんとかする、なんとかすべきという押しつけは、東日本大震災という「厄災」を経て、むしろ強まっている気がする。
たとえば少子化問題を見てみよう。少子化傾向が止まらず、このままだと日本の人口は減少の一途をたどると危機感を持って報道され続けている。首相は二〇二三年三月末には、「異次元の少子化対策」を打ち出す、と宣言した。
もう二〇年以上前から人口動態や出生率に関する統計から、日本は少子化対策に本腰を入れないと大変なことになると言われ続けてきた。警鐘が鳴らされ続けてきたにもかかわらず、保育園は増えず、シングルマザーの貧困化は歯止めが利かず、男性の育休取得率は上がらず、夫婦別姓は遠のき、ジェンダー平等達成は見通しが立っていない……。
少子化対策は女性対策であることをわかっているのだろうか。女性が生きていくうえでの障壁をなくすことに対して冷酷ともいえる無策ぶりを発揮し、状況を放置しつつ、いっぽうで子どもの数を増やしたいために、婚活支援をして未婚男性を減らすための目先の対策に予算を使う。物価高で、給与は上がらず、円安は進行しているのに、結婚して子どもを産むなんて無理と思う女性は多いだろう。
さまざまな問題をすべて家族というブラックボックスに放り込むことで、政策的には何も進展させてこなかった。そのつけが出生率の低下に表れているのではないか。もっと過激なことを言えば、それは「女性たちの復讐」ではないか、そう思えるのだ。
WHОによるパンデミック宣言後、各国でロックダウンが実施された。人気の絶えた街の光景はパリもベニスも日本とそれほど変わらなかったが、テレビのニュースで、閑散としたルーブル美術館脇の並木道を歩いている人が、馬に乗った警官から注意を受けているのを見て驚いた。国家権力によって在宅することを明確に強制されていたからだ。やんわりと家族に、そして「世間」という同調圧力にまかせて、決して強制しなかった日本との違いを見た思いだった。
東京都心でも車の数は少なく、見上げた空は、帰省で人々が街からいなくなった正月三が日のように澄んだ色をしていた。ゴーストタウン化した繁華街は、東日本大震災が起きた翌日の原宿の街のようだった。
コロナ禍で家族に何が起きたか。今に至るまで不可視な部分は多いが、どの国においても、それほど変わりはなかったのではないか。あの人気の途絶えた街角の光景は、強制かどうかにかかわらず人々が家庭に閉じ込められたことを意味していたからだ。
マスクは家庭内に一歩入ったとたん、玄関で外すことができた。飛沫を飛ばして食事をしてもとがめられることはなく、夫婦であれば性的接触はあたり前のことだった。これほど私的空間が例外的扱いを受けたことはなかったのではないか。街に出ることを禁じられて家の中(私的空間)に閉じ込められる。家族全員が顔を合わせて暮らす時間には、あらゆる社会的規制が及ばなかった。飲食店などに課されたような徹底的な感染症対策や監視から自由だったのが家族だった。その結果として、日本でもヨーロッパでも家庭内で閉塞感が高まり、DV相談件数は激増した。
家族の暴言・暴力の増加に加えて、一日中家族全員が在宅することで生じる新たなケア役割を誰が担うかが問題となった。結果的に多くの家庭では中高年女性にそれが集中し、一部は自死にまで追いつめられた。逃げ場のない状況の中で自死を選ぶ一〇代の女性たちも増えた。
新型コロナ感染症がインフルエンザと同じ分類になれば、人々はコロナ収束を実感し、久しぶりの旅行やイベントに繰り出すだろう。バラや藤の花が咲き誇る五月の陽光のもと、あんな苦しかったことは忘れたい、もう忘れてしまった、人々のそんな思いが募るだろう。
しかし「過去のことになった」「思い出したくもない」という空気が高まるころから、皮肉にも、コロナ禍が様々な分野に与えた影響が明らかになるのではないか。
先日、東京の青山をタクシーで走ったが、きらびやかなガラス張りのブランドショップが いくつも閉店していたのに驚いた。日本で一番おしゃれなエリアがところどころ綻びている光景は、コロナ禍の無残な爪痕に思えた。
パンデミックが子どもたちの成長に与えた影響、経済に与えた影響についての調査・研究は今後始まるだろう。しかし家族へのそれはどうだろう。この間で事態に慣れ切ってしまったかのような人たちは、もうなんでもない、トラウマ的影響なんかあるはずもない、そう考えるのではないか。
第二次世界大戦の長期的影響を、「戦争と文化的トラウマ」という視点から研究した成果が書籍化された(竹島正・森茂起・中村江里編『戦争と文化的トラウマ』日本評論社、二〇二三)。そこには戦争体験がトラウマとしてどれほど長期にわたって影響を与えつづけるかについて、多方面から論じられている。
歴史的視点からトラウマを考えるそれらの本を読むたびに、過去を忘れ前向きになりたいというベクトルには、それと正反対の方向へと私たちを引き戻す力が働いていることがわかる。―つまり過去を忘れようとすればするほど、過去の記憶はよみがえり、私たちをつかみ、まだ終わってなどいないとばかりに引きずり戻してしまうのだ。この国では「水に流す」「いつまでも過去にこだわるな」という言葉が賞賛されるが、それは積極的に忘却を試みることで無感覚になってしまうことを意味するのではないだろうか。それはトラウマからの解放ではない。ずっと「あの時」のままに過去がなまなましく生き続けるとき、それに蓋をしようとすればするほど現在の私たちは有形無形に苦しめられる。だからこそ、痛みを抱え続けている人が過去と向き合い、経験を自分なりにとらえなおそうとするプロセスに、私は希望を見る。
これまでの私の著書と同じく、本書も家族が大きなテーマになっている。書きながら考え、考えながら書く。このスタイルも同じだ。
しかし今回ほど、書きながら状況が変化し想定外の事態が出現したことはなかった。デルタ株、オミクロン株の流行、それに伴うワクチン接種奨励といった変遷に加えて、二〇二二年二月にはロシアがウクライナに侵攻を開始したのだった。キエフが突然キーウと呼ばれ始め、ウクライナの歴史を改めて振り返る人も増加した。戦闘のニュースに胸を痛めながら連載中、原稿を書いたことをおぼえている。世界規模の変動と、家族というプライベートな場に生じる変化が、私の中で輻輳し、呼応していた。
本書に登場するのは全員女性である。そして、登場する人物は、私が出会った多くの人たちから造形しなおした、実在しない人物であることを最初にお断りしておく。このような定型的な前置きを書くことはあまり好みではないが、私たちの職業倫理上不可欠な前提なので、この点を強調しておく。私個人としては、むしろお読みになって「これって私かも」と思う人が多いことを願っている。私は、何かを変えたい、変えなければ苦しくて生きていけないと訴えてカウンセリングにやってきた女性たちのことを、いつも念頭に置いていた。コロナ禍は彼女たちの変化を加速させた。空気圧が倍になるように、家族関係において溜まったものが濃縮・凝縮されて噴出したかのようだった。
その変化の波が押し寄せた時、彼女たちは正面からそれに向かっていった。もともと逃げ道などなかったからかもしれないが。そうして、彼女たちはちゃんと生き延びていったのである。そのことに、私は胸が熱くなった。
コロナ禍という厄災が家族に何をもたらしたか。どのような変化を与えたのか。今後、新 たな困難、混乱に見舞われた時、家族はどんな方向に向かっていくのか。それらの問いに答えようとした一冊として、本書がずっと読まれつづけることを願っている。
(転載禁止)
版元から一言
パンデミック、甚大な自然災害、ウクライナ侵攻…。もっともプライベートな存在である家族に、これらの変化はどんな影響をもたらしたのか。世界規模の変化がめまぐるしく起きるなかで書き継がれたエッセイ。リアルなエピソードと、社会学、女性学的に日本の社会を鋭く考察する視点が交差する一冊。大きな話題を呼んだウェブ連載の書籍化にして、2年半ぶりの著者の新刊単著。
上記内容は本書刊行時のものです。