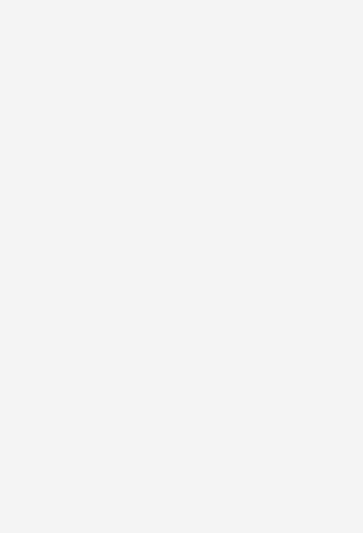書店員向け情報 HELP
出版者情報
書店注文情報
在庫ステータス
取引情報
超看護のすすめ
ナイチンゲールの復権とケアの哲学
- 出版社在庫情報
- 在庫あり
- 初版年月日
- 2019年12月3日
- 書店発売日
- 2019年12月10日
- 登録日
- 2019年10月17日
- 最終更新日
- 2019年12月5日
紹介
看護の課題を、人文学の側から真摯に、そして平易に語りながら、患者と看護者のあいだに新たな関係を築く、〈超看護〉という新しいあり方について――。
「文化人類学・文学・哲学」と「ナイチンゲールの思想」とを同時に考え、〈看護とは何か〉、そして〈生きることと死ぬことの意味〉について語る。
また、精神的な病とナラティヴ(物語)の関係性をあきらかにするなど、これからの看護の未来をわかりやすい言葉でえがき、ますます喫緊の課題となっている〈医療と看護のあり方〉にあらたな側面から光をあてる。
看護を志す学生や看護への新しいアプローチを模索する看護師や研究者、そのほか今まさに看護の現場に直面し悩んでいる一般の方たちのための一冊。
目次
まえがき
Ⅰ 「超看護」の論点
第1章 「看護の詩学」とナイチンゲール
第2章 「看護の脱構築」試論
第3章 「アメリカの看護」という遺産
第4章 「死」は恐ろしいことなのか?
第5章 「前近代」から学べるもの
Ⅱ 「超看護」の感性
第6章 「地理的身体論」序説
第7章 「闇」が教えてくれる世界
Ⅲ 「超看護」の広がり
第8章 「里山看護」について
第9章 「信州伊那谷」から考える
あとがき
前書きなど
まえがき
いまから一年前の二〇一八年一〇月二四日に、母が他界しました。八一歳でした。亡くなるまでの六年間ほどは、グループホームに二カ所、その後、認知症を専門とする病院に入院し、結果的にそこで息を引きとりました。この期間は、徐々に認知症が進行していく期間とも重なっていました。
「胃瘻〔いろう〕(胃に直接栄養を入れるために腹壁と胃に開けられた孔)のような延命措置はしないでほしい」と医師には告げてありましたので、経口摂取(口からの栄養補給)ができなくなると水分だけの点滴に移りました。
「ものを口から食べられるというのは人間にとっては大きな快楽で、これができなくなるのは〈生〉から一歩遠ざかることになる」という話を、ある看護師さんの体験談として聞いていましたので、すこし悲しくなったことを覚えています。
やがて、頻回〔ひんかい〕に点滴が漏れるようになる頃には(あちこちに刺された腕や手の甲は内出血がありました)徐々に痩せ衰え、見るからに弱っていき、最期は眠るように旅立ちました。
「ボケる」というのは、旅立つ方も旅立たれる方も、心と体の準備をするには良い期間なのかもしれません。これが、突然の死だったら、私はもうすこし取り乱していたことでしょう。
本人は、認知症によって死への恐怖もだんだんと和らぎ、看取る側も覚悟を決めていく。生と死の向かう方向に逆はありませんから、その困難な道をどのように歩んでいくかは、誰にとっても大きな問題です。
これまで数え切れないほどの人間がその道を歩いてきたというのに、私たちはいつでも、まるではじめてその道に立たされているかのごとく、右往左往しています。
人類が長いあいだに蓄積してきた「知恵」をないがしろにして、新しい「何かよいもの」を求め続けて生きている、というわけです。
日本は、たとえばイギリスなどと比べると「胃瘻」から栄養補給をして命を長らえる人が多く、肌の色艶はよくて健康そうでも、意識はないままに命を長らえている人がいます。国によってはそのような手段(胃瘻、腸瘻など)を極力とらないようにしているところもあります。
はたして、人工的に延命をするのは不自然なことなのか、あるいは、人類の叡智なのか。人の死の間際にはさまざまな思いが交錯し、宗教的なことや政治的なことも絡み「安楽死」を選ぶ人たちのことなども自然と頭に浮かんできます。
私自身は、母に対して胃瘻などの延命の方法を選択しませんでしたが、特段、そのような措置を批判しようとは思いません。なぜなら、意識がなくても身体は温かく、そうやって「生きている」という事実だけで、家族によっては「生きる希望」に変えられる人もいるからです。
それにしても「男」というものは、思春期以降は母親に触れる機会など滅多になく、もしかすると「こういうとき」まで母親の身体に触る機会などないかもしれない、そんなことを思いながら、病室で母の手や足をさすっていました、ときには顔も。そういう時間をとれるのも良いものだ、と心のどこかで感じていました。
母は妹に見守られながら息を引きとり(私は「死の瞬間」には立ち会えず、三〇分後くらいに駆けつけることができました)、あっという間に顔から血の気が引き、手足が氷のように冷たくなっていました。「ああ、もうここにはいない別世界の人間になったのだなあ」とそのとき実感しました。
人によって死に方は一様ではないし、看取る方も一様ではありませんが、変わらないのは、さっきまで動いていた身体が動かなくなり、温かかった身体が冷たくなることです。
頭でっかちの私は「死」を観念で弄ぶことには長けていました。しかし、結局「死」は物理的な変化であり、そして「記憶」なのだということに思い当たりました。
母の死と直面しながら、お互いの人生を振り返れば、私は今までの人生を通して父を含むさまざまな人たちから「もっと普通に生きなさい」「その生き方は間違っている」などと言われ続けてきましたが、そのような私の好き勝手な生き方を、母はいちども否定することはなかったことに気づきました。
それどころか、いつでも応援し、守ってくれました。そんな母との「無数の出来事によって彩られた記憶」がそこにはあったような気がします。母の存在がなければ私はいまこうして文章を綴り続けることもなく、誰かの欲望を自らの欲望と勘違いしながら、それはそれで幸せな人生を送っていたことでしょう。
ディズニー映画の『リメンバー・ミー』(二〇一八年)は、メキシコの「死者の日」をテーマに展開する物語で、中心におかれたメッセージは、人は「二つの死」を迎えるというところにあります。一つ目は肉体の死。二つ目は、その人が誰からも〈記憶〉されなくなることによって迎える死。
これによって、その人はもう生きていたときのすべての存在がこの世界から消去されます、永遠に。そのような人物がこの世に存在していたのかさえも、もう誰にもわかりません。人は誰かに覚えておいてくれることによって、かろうじて「記憶」のなかでいつまでも生き続けることができるのです。
一年経ったいまでも仏壇の横に大きな写真を飾り、毎朝、線香をあげ、手を合わすたびに思い起こし、私の記憶のなかで父と母はたしかに「生きています」。
学問は、それを行っている者の生活や人生と切り離して考えることはできませんし、また、そうあってはならないと思います。吸収した情報や知識を「操作」することによって、形式だけの一丁上がりの論文や文章に意味があるとは私には思えないでいます。自分から出た言葉はすべからく「私」が抱えた「疑問や矛盾」に自ら答えようとするものでなければならないとも思います。
母との特別な時間を過ごした日々は徐々に時間が成熟する期間でもありましたが、同時に仕事場で「看護」の世界にすこしずつ入り込む時期とも重なっていました。「生身の人間」にやがてかならず訪れる複雑で不思議で難しい問題について考えるには最適な職場だったと振り返っています。
こうしてひとまずたどり着いた地点で周りを見渡しながら、いくつかの文章を残してみようと思いました。看護の世界に慣れ親しんでいない者には看護はこう見えるのかと捉えていただいてもいいですが、私にとってはどれも欠かせない大事なポイントであることは間違いありません。奥深くて興味が尽きないこの看護の世界に対して、心からの敬意をもって真剣に取り組んだつもりです。
そしてそれらへの関心から生じる疑問はいまでも解決されたわけではありません。いまだ道の途中です。こうしてたどり着いた場所で、誰かから「それは違う」と言われても、私がたしかに感じてきたことだけは変わりません。それら私固有の問題意識を、思いがけなく誰かと共有できる点があるとしたならば、筆者としてそれ以上に嬉しいことはありません。
本書は三部に分かれています。一部は私が「超看護」と名づけた内実の基本的なスタンスをいくつかの論点をもとにして説明しました。二部は「超看護」の根底にある感性のあり方を「文学」などをもとにして説明を試みました。三部は「超看護」と同じ方向性をもつ里山看護について、信州伊那谷の土地を媒介にさまざまな話題を通して問題提起を行いました。
版元から一言
本書は、どの家庭にとっても大きな課題となりつつある〈看護〉について、医学や医療としての側面からだけではなく、文学や民俗学、そして人類学や哲学といった人文知の側から考え示された、〈超看護〉とも呼びうるまったく新しい看護のあり方が語られています。
著者自身の母の看護の経験、そして著者が所属している長野県看護大学の学生や教員や看護師との長きにわたる交流から本書は生まれています。
看護を志す学生や看護への新しいアプローチを模索する看護師や研究者、そのほか今まさに看護の現場に直面し悩んでいる一般の方たちのための一冊です。
書籍のデザインや造本も努力を重ね、丁寧に作りました。ぜひ手にとってご覧いただけますと幸いです。
上記内容は本書刊行時のものです。