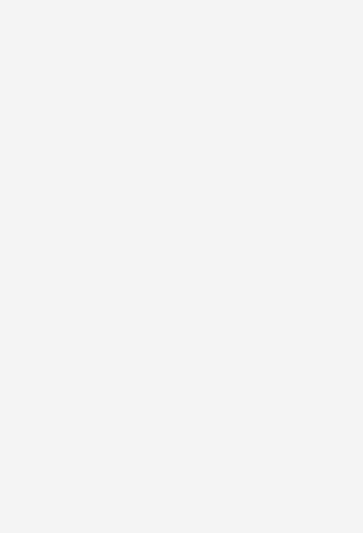書店員向け情報 HELP
出版者情報
書店注文情報
在庫ステータス
取引情報
死を想え メメント・モリ 多死社会ニッポンの現場を歩く
- 出版社在庫情報
- 在庫あり
- 初版年月日
- 2020年3月20日
- 書店発売日
- 2020年3月18日
- 登録日
- 2020年2月5日
- 最終更新日
- 2020年3月24日
書評掲載情報
| 2020-05-31 |
京都新聞
評者: 鎌田慧 |
| 2020-05-16 |
高知新聞
評者: 鎌田慧 |
| 2020-05-16 |
陸奥新報
評者: 鎌田慧 |
| 2020-04-12 |
中日新聞
評者: 島薗進 |
| 2020-04-12 |
東京新聞/中日新聞
朝刊 評者: 島薗進(上智大学グリーフケア研究所所長、東京大学名誉教授) |
| MORE | |
| LESS | |
紹介
年間130万人以上が亡くなる社会で、いったい何が起きているのか。無縁化する墓、不法投棄される遺品、孤独死、延命治療、医療過疎……。死を扱う現場や死に直面した市井の人々の取材を通して見えてきたのは、社会の大きな変化と、それに追い付いていない制度や法の不整備だった。それらを変えなければ、誰もが安心して人生を終えられる社会は実現しない。多死社会の現実と課題を浮き彫りにした好評連載、待望の書籍化。
目次
まえがき
第1部 遺すもの、遺されるもの
1 亡骸を追う――残骨灰を知っていますか?
もう一つの遺骨――知られざる逝き先
金とスラグ――灰に眠る貴い鉱床
処理のコスト――なぜ止まらぬ1円入札
北の地での争奪戦に政治の影
法のはざまで戸惑う自治体
2 消えゆく墓――守れない、もてない、もちたくない
墓の墓場
砕いて解体される墓――墓は消えても遺骨は残る
法の波間に埋もれる散骨
納骨ビジネス――もどかしい線引き
増える無縁墓――片付けられない事情
檀家が減って寺院は存続困難に
3 遺品の行方
公営住宅4号室――暮らしの跡、処分に壁
新規参入相次ぐ整理代行――故人の品が再び世へ
遺品、海を渡る――ユーズド・イン・ジャパンが人気
遺品整理業者をめぐるトラブル――不法投棄や高額請求
生前に家じまい――子どもに迷惑かけたくない
4 自分を遺す
遺贈寄付――最後に「誰かのため」という思い
新規登録が相次ぐ献体――医療の世話になったから
無効となった自筆遺言――思わぬ壁に
変わらぬ姿でお別れ
夫とは別の墓に入りたい――やっと自由になれる
第2部 旅立ちのとき
5 最期を決める――延命治療をめぐって
延命治療、どうしますか――母の呼吸器を外した姉妹の決断
意思の疎通がはかれなくなったら――あるALS患者の訴え
身寄りのない高齢者の終末期――老いるニュータウンの現状
認知症のある人の意思は誰が確認するのか
覚悟を決めて在宅での看取り――悔いのない最期とは
痛みから解放され眠るように―セデーションという選択
生き続けるという意思――あなたがいるから
6 別れのあとで――遺族の揺れる思い
本当に延命しなくてよかったのか
夢でも妻に会いたい
病名を知らず逝った母
他の遺族と語らい、救われた
夫亡きあと、在宅を支えるボランティアに
7 ひとりで逝く――つながりが失われるなかで
保冷室で三週間―引き取り待つ遺体
最期の部屋から――生活再建途上での孤独死
町内会長の憂い――交流なく気づけなかった
〝身内〟のような他人との契約――後始末をだれに
終のすみかで施設の仲間と眠る
8 人生を締めくくる準備―星野公平さん、がんで逝く
治療断念後、葬儀の段取りを進めた
運命を受け入れるまでの闘い
家族で死に向き合う
死は悲しいけれど、幸せの真逆ではない
夫の遺したつながりを大切に
9 「終」を支える人々
訪問看護師――旅立つ舞台を演出する
介護職員――逝く人と向き合う
ホームホスピス――自然な死の受け皿に
派遣僧侶――ネットで新たな縁
臨床宗教師――本音聞き、心を癒やす
10 「終幕の地」はどこに
家ではなく緩和ケア病棟で――家族への気遣い
緩和ケア病棟がない――入りたくても入れない地方の現実
災害公営住宅――亡き息子と故郷で一人暮らす不安
死後を誰にも託せず、亡くなる人々――身寄りのない高齢者
医療過疎の島にあえて帰る――故郷で亡くなった漁師の最期
スペシャルインタビュー
ヨシタケシンスケ さん
あとがき
前書きなど
あとがきより一部抜粋
本書に収録した連載「メメント・モリ」の取材班が立ち上がったのは、二〇一七年の秋でした。平成が終わりを迎える二〇一九年に向け、自分たちが生きているこの時代を何を軸に切り取るのか。議論を重ねる中で、全員の頭と心に浮かんだのが「多死社会」でした。「終活」という言葉がユーキャン新語・流行語大賞のトップテンに選ばれたのが二〇一二年。五年がたち、エンディングノートなど身じまいに関するセミナーが盛んになった時期でもありました。
しかし、「メメント・モリ」が目指したのは、新しい死生観や葬儀のスタイルなどをランダムに紹介する連載ではありません。死を巡る「現場」と「人」に徹底的にこだわり、多死社会の実相に筆を近づける。それが、取材班が共有した連載の主旨です。自分たちの両親も友人も、今ここで議論している記者も、人はいつか必ず死ぬ。記者として、一人の人間として、逃れようのない現実と正面から向かい合い、取材で得た赤裸々な事実を伝えて読者と一緒に考える。タイトルが意味する「死を想え」は、社会や読者に対してだけでなく、取材班が自らに向けたテーマでもありました。
では具体的にどの現場に立ち、何をどう伝えるのか。最初のテーマに取り上げ、本書の第1部に収めた「亡骸を追う」は人間の最後の姿である残骨灰の行方を追跡しましたが、その取材の中で記者から伝え聞いた忘れられない言葉があります。
火葬場で亡骸が炎に包まれる様子から書き始めた「もう一つの遺骨」の取材の日。喪服を着た若い記者とカメラマンは口数が少なく、こわばった表情で現場に向かいました。炉の裏側にある小さな窓に顔を近づけてすべてを取材した記者たちに、火葬場の所長は「技術のある職員がしっかりやっていることを、少しでも社会に知ってほしいという気持ちがあります」と言いました。そして、こう続けたそうです。「顧みられることのない現場ですが、死は誰にも避けられないものでもあります」
この言葉に気づかされたことがあります。亡骸を追ったシリーズだけでなく、放置されて荒れている無縁墓や引き取り手がない遺品、宙に浮く遺言、孤独死、遺された家族の苦悩など連載全体に共通しますが、生々しい現実を伝える記事が読者にどのように受け取られるのか、不安がまったくなかったといえば嘘になります。「遺」、「墓」、「死」、「悲」という文字が数多く登場する記事に、嫌悪感をもたれるのではないか。予想はしていましたが、読後感が決して良いとはいえない内容に、読者からは「朝から気分が悪い」という電話やメールが寄せられました。
ただ、「将来どうしたらいいだろうと考えるようになった」、「ようやくこの問題が取り上げられた」など、前向きに受け止めていただいた反応が多かったのも事実です。「タブーだと思っていただけに感謝する」と書かれた手紙もいただきました。この手紙の指摘通り、私たちメディアは死の現場を直線的に報じることを、どこかでタブー視してきたのかもしれません。「忌み」には「洗浄」と「穢れ」がありますが、事件や事故とは別の死に触れることを「禁忌」とし、気づかない間にある意味で自主規制をしてきたのではないかと思います。それだけに、「知ってほしい」、「顧みられることのない現場」と話してくださった火葬場の所長の言葉は、連載が進むごとに胸に重く響きました。
もう一つ、分かったことがあります。メディアが死を取り上げることをどこかでタブー視してきたとするならば、国は深刻な課題を棚上げにし、対応を自治体に頼り切っているという実態です。年間死者数が今後も増えると予測する半面、法律や政策は追いついていません。自治体が業者に処理を委託している残骨灰が0円で取引されている事実を裏付け、法規定や国の統一基準がないのか質問した記者に、厚生労働省と環境省のそれぞれの担当者は「法律も監督官庁もない」「最終的には自治体で判断してほしい」と言い切りました。公営墓地に立つ無縁墓や公営住宅に残された遺品の処分などにも基準はなく、すべて自治体に任せています。現場で苦悩する自治体職員の間には、議論と対応を国に求める強い声があります。連載開始後の民法改正で自筆証書遺言の要件が緩和されるなど、すべてが置き去りにされているわけではありません。宗教的感情が絡み、一律の基準が難しいことも理解しています。ただ、少子高齢化と多死社会が同時進行する陰で、故人の尊厳に対する国の姿勢はあまりに冷たくはないでしょうか。
その一方で、人は強く生きようとしています。がんを患い、二〇一八年十月二十七日に六十九歳で亡くなった三重県桑名市の星野公平さんと家族の皆さんは、第2部に収録した「人生を締めくくる準備」の取材を申し入れた記者に「全部、見てほしい」と話し、生前から亡くなった後までのすべての取材に協力してくださいました。
星野さんだけではありません。自らの命に限りがある中で、記者の踏み込んだ質問にも思いを打ち明けてくださった方々。延命措置の判断を迫られ、苦悩の中で母の人工呼吸器を外す決断を話してくれた姉妹。生前の意思を尊重して最後の別れ方を決めたはずなのに、本当に良かったのだろうかと答えを出せずにいる夫や妻。引き取る家族がおらず保冷室で三週間を過ごした友人の遺体を、たった一人で見送った男性……。一人一人の言葉はそれぞれの人生そのものであり、悲しみを超えて前に進もうとする尊い証言です。
上記内容は本書刊行時のものです。