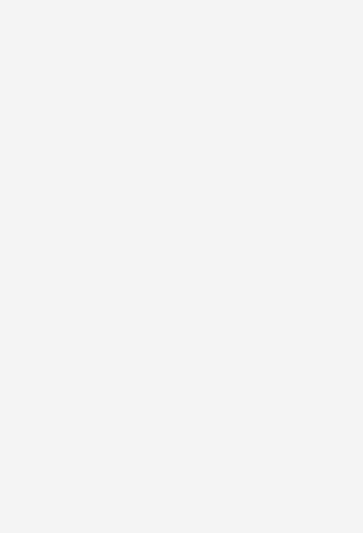書店員向け情報 HELP
出版者情報
在庫ステータス
取引情報
神の火を制御せよ 原爆をつくった人びと
原書: COMMAND THE MORNING
- 出版社在庫情報
- 在庫あり
- 初版年月日
- 2007年7月
- 書店発売日
- 2007年7月24日
- 登録日
- 2010年2月18日
- 最終更新日
- 2014年7月4日
書評掲載情報
| 2019-12-01 | 東京新聞/中日新聞 朝刊 |
| MORE | |
| LESS | |
紹介
1940年、アメリカには、アインシュタインをはじめヨーロッパからの亡命科学者が多数いた。 彼らは核兵器の破壊力を知らないアメリカ政府に口々に訴える。「ナチスが核兵器を作っている! ナチスが核兵器を完成させたら大変なことになる!」
「原子爆弾を使うことにはならないとお考えですか」
「使うか否かにかかわらず、アメリカは原子爆弾をつくるべきだ。それもできるだけ速やかにね」
アメリカ政府は、彼らの声に押されるようにして原爆の開発を開始。若い女性科学者ジェーンや青年科学者スティーブは、原爆の開発・兵器として使用に反対する。
「核兵器の製造には加担したくありません」
「誰が好きでやるものか。悪魔の仕事だ。だが、ほかの悪魔が先に作ったらどうする?」
原子爆弾という最終兵器があれば、使わずとも戦争そのものを終わらせることができるかもしれない。そこに望みをつないで開発を進める彼らは1945年7月16日、ついに世界初の原爆実験を成功させる。
「やったぞ」バートは絶叫した。「やったぞ。我々は成功したんだ」
彼はスティーブの肩に腕を投げかけ、泣き笑いを始めた。
「新しい神の世界だ」バートはすすり上げた。「新しい天と地……みんな、これは黙示だ!」
「新しい時代には違いないが、果たしてそこは神が住む世界だろうか」スティーブは暗い気持ちで反問した。
原爆実験の成功を知った アメリカ政府は、日本への原爆投下を決定。
アメリカ政府に原爆を開発するよう働きかけてきたハンガリーの亡命科学者は、原爆の使用に反対する署名を集めるために駆けずりまわる。
「原子爆弾を使う必要はない。日本は必ず降伏する。すでにひざまずいている。日本人は誇り高い民族だから、無条件降伏なんか言い出しちゃならない。ただの降伏でいいじゃないか。それなら彼らの名誉が保てる。そうじゃないか? 戦争を終わらせることが大切だ。そうじゃないか?」
「投下はやめて、お願い」ジェーンは両手で顔をおおい、スティーブもまた投下をくい止めようと、ビラを撒いて日本政府に降伏を呼びかける。
1945年8月5日、ワシントンは蒸し暑い夏日だった。熱気を含んだ雲が上空に垂れこめていた。依然として日本から返事は来なかった。陸軍長官は特別警告を発し、さらに大量のビラをまいた。その日が暮れたが回答はなかった。真夜中に憔悴しきった長官は口を固く閉じた若い科学者のほうを向いた。「スティーブ君」声は穏やかだった。「やれることはすべてやった。研究所へ戻りたまえ」
恋愛・苦悩・スパイ・夫婦の確執……
原爆を作った人々の愛と葛藤を描いた問題小説。
被爆国に生きる我々は、この小説をどう読むのか!
目次
1章 大統領の決断9
2章 真珠湾攻撃の翌朝135
3章 カウント・ゼロ213
4章 原子爆弾投下281
エピローグ387
解説390
前書きなど
HIROSHIMA! ヒロシマ!
「原子爆弾を落としたことを、どう思いますか?」アメリカ軍の若い爆撃手に新聞記者が尋ねた。
「どう思ったかって?」
爆撃手は同じ言葉をくり返し、タバコを深く吸いこんで煙の輪を吐き出した。
「ふつうの爆弾と変わりないですよ。それだけです」
──その日、死の町で、一人の生存者が壕からはい出し、立ち上がって辺りを見回した。男は煙が立ちこめた死と破壊の砂漠に立っていた。男は号泣し、絶望のうめきを発し、天に向かって両手を振り上げて叫んだ。
「こんな、こんな惨いことがあっていいのか!」
版元から一言
この小説は、日本人がこれまで読んだことがない「原爆小説」だ。
原爆を作った科学者・その妻・美貌の女性科学者・スパイ・実験中の被爆事故……。あらゆる要素が絡まって、私たちは、まるでエンターテイメント小説を読むようにして、この原爆小説を読むことになるだろう。
本書は、被爆者の側から描かれた日本の「原爆小説」とは異なる、加害者の側から描かれた「原爆小説」なのだ。
登場人物の多くは実在の科学者をモデルにしているが、本書はドキュメンタリーではない。ノーベル賞作家にして大衆小説家であるパール・バックは、原爆を作った人々を活き活きと描きだし、私たちは、いつの間にか、原爆を作った人々に感情移入しながら読み進めることになる。
自分がもし原爆を作る使命を課せられた科学者だったら、どうしていたのか──。この小説が突きつけてくるこの問いをくぐり抜けて始めて、私たちは原爆を世界に向けて語ることができるようになるのかもしれない。
上記内容は本書刊行時のものです。